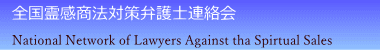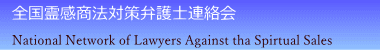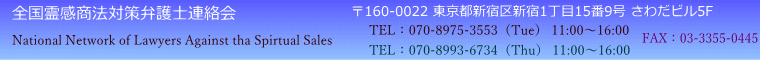|
全国霊感商法対策弁護士連絡会
|
代表世話人 弁護士 郷路征記(札幌)
代表世話人 弁護士 中村周而(新潟)
代表世話人 弁護士 河田英正(岡山)
代表世話人 弁護士 平岩敬一(横浜)
代表世話人 弁護士 山口 広(東京) |
| 事務局長 弁護士 木村 壮(東京) |
| 第1 声明の趣旨 |
| |
1 世界平和統一家庭連合(以下、「旧統一教会」という。)等に対して |
| |
|
① 旧統一教会は、不当な献金等の勧誘による経済的被害や家族破壊、2世等に対する人権侵害等、自らが生み出してきた過去の被害・被害者に真摯に向き合い、これに誠実に対応し、謝罪の上で損害の一切を賠償するよう求める。 |
| |
|
② 旧統一教会は、旧統一教会が行って来た不法行為等に関する正当な言論に対して、これを封殺するために不当な損害賠償請求訴訟を提起したり、発言者を誹謗中傷したりするなどの威迫行為を行わないよう求める。 |
| |
|
③ 海外のごく一部の有識者の中に、日本の旧統一教会による被害の実情を知らず、あるいは理解しようとせず、旧統一教会による被害の救済または抑止に向けた行政や被害者らの活動等について「宗教迫害」などと決めつけ、ことさら旧統一教会を擁護する発言等が散見される。しかし、これらの発言等は、旧統一教会側の主張のみに依拠して、日本の実情を調査せずになされたものであり、あまりにも不公平かつ軽率である。 |
| |
|
そこで、旧統一教会を無批判に擁護する有識者らに対し、強く抗議するとともに、被害者の実情を調査せず、不公平かつ軽率な言動を行わないように強く求める。 |
| |
2 国等に対して |
| |
|
⑴ 不当寄附勧誘防止法の見直しについて |
| |
|
政府及び各政党に対し、不当寄附勧誘防止法附則5条に基づき、かつ、参議院附帯決議の趣旨を踏まえ、政府部内に検討会を設ける、または、与野党で協議する等して、速やかに不当寄附勧誘防止法の見直しの検討を開始し、法改正をするよう求める。
法改正にあたっては、①旧統一教会が行って来た違法不当な献金勧誘の手法に即した禁止行為を設定すること、②際限なく献金をさせられている信者と生活をともにする配偶者や子どもたち等の家族の被害を抜本的に救済できる制度を創設すること、③行政による迅速かつ実効的な被害救済、被害抑止ができるよう、行政措置の要件及び措置基準を見直すこと、④法の適用対象を個人や代表者等の定めがない宗教団体に拡大することを求める。 |
| |
|
⑵ 解散命令及びその後の清算手続について |
| |
|
|
① 最高裁判所は、令和7年3月3日、質問権行使に対する回答拒絶について文部科学大臣が旧統一教会に過料を科すよう求めた手続において、「民法709条の不法行為を構成する行為は、(宗教法人)法1項1号にいう『法令に違反』する行為に当たる」と判示した。
東京地方裁判所においては、かかる最高裁決定を踏まえ、速やかに解散命令を発令するよう求める。 |
| |
|
|
② 国に対し、宗教法人法81条1項1号ないし2号前段を理由とする解散命令が確定した場合、その後の清算手続のために選任される清算人の権限強化を図るため、立法等の措置を講じるよう求める。
|
| |
|
|
③ 国に対し、宗教法人法81条1項1号ないし2号前段を理由とする解散の場合に、清算結了後に脱会する信者の被害救済の途が残されるよう、清算手続終了後の残余財産の処分について必要な法整備等を講じるよう求める。 |
| |
|
⑶ 「宗教等2世」等の家族被害の問題について |
| |
|
|
① 子ども家庭庁、法テラス等に対し、自治体等とも連携して、「宗教等2世」がその所属する団体に対して損害賠償請求権等の権利行使により被害回復を図ることができるようにするための相談体制の整備等の対策を講じるよう求める。 |
| |
|
|
② 国に対し、「宗教等2世」に対する宗教法人等による理不尽な人権侵害に対して適切な慰謝料額が賠償されるよう、慰謝料額算定の適正化のための必要な立法措置等を講じるよう求める。 |
| |
|
|
③ 声をあげた「宗教等2世」も含めた被害者ら、もしくは旧統一教会の被害者らの救済に誠実に取り組んできた当連絡会所属の弁護士を含む被害者関係者らに対して、旧統一教会関係者らによる誹謗中傷等が行われている。 |
| |
|
|
そこで、行政、警察等の当局は、誹謗中傷等についての被害相談を受けた場合には、そのような違法行為が行われないよう、当該誹謗中傷に対して速やかに厳正かつ適切な対処をするよう求める。 |
| 第2 声明の理由 |
| |
1 旧統一教会等に対する声明の理由 |
| |
|
⑴ 声明の趣旨①について |
| |
|
|
旧統一教会は、現在においても、霊感商法や高額献金による被害は、当連絡会が旧統一教会を壊滅することを目的として作り出したものであるとして、「被害」は存在しないと主張し続けている。そして、旧統一教会は、文部科学大臣による東京地方裁判所に対する解散命令請求や報告徴収質問権の行使等ですら、旧統一教会の信教の自由に対する侵害行為であると非難している。また、その信者らは旧統一教会の信教の自由が侵害されているとして全国各地で街頭演説やデモ行進、チラシ配布等を行い、旧統一教会が被害者であるかのように喧伝している。
しかし、旧統一教会が違法な献金等の勧誘行為によって多数の信者らに対して甚大な経済的被害を生じさせ、多くの家族を破壊し、また、2世に重大な人権侵害を生じさせたことは明白な事実である。坂本堤弁護士が信教の自由を主張するオウム真理教に対して「人を不幸にする自由などない」と述べたのと同様に、旧統一教会に、違法な献金勧誘や家族破壊、2世に対する人権侵害をする自由は存在しない。
そこで、当連絡会は、改めて、旧統一教会に対して、自身が生み出した過去の被害・被害者に真摯に向き合って、これに誠実に対応し、謝罪の上で賠償することを強く求める。 |
| |
|
⑵ 声明の趣旨②について |
| |
|
|
旧統一教会及びその関連団体等は、ジャーナリストや弁護士等に対し、それらの者の旧統一教会等に対する正当な言論活動が名誉棄損等に当たるとして不当に高額な損害賠償を求める訴訟を提起して来た。このような訴訟提起は正当な権利行使とはいえず、旧統一教会に敵対するジャーナリストや弁護士、そして、マスコミ等の言論を委縮させるという不当な目的を持って行われたものであることは明白である。
また、このような旧統一教会の言動に呼応して、旧統一教会に敵対するジャーナリストや弁護士のみならず、被害を訴えた元信者や2世、家族に対してまで多数の誹謗中傷がなされている。
そこで、旧統一教会に対して、訴訟提起等によってジャーナリストや弁護士、そして、マスコミ等の言論の委縮、元信者や2世、家族による被害申告の躊躇を図るのではなく、まずは自らの生み出した多数の甚大な被害に真摯に向き合い、謝罪と反省の意を公に表明するよう求める。 |
| |
|
⑶ 声明の趣旨③について |
| |
|
|
海外の有識者の中に、日本の旧統一教会の被害の実情を知らず、あるいは理解しようとせず、旧統一教会に対する行政や被害者らの活動等について、「宗教迫害」などと、ことさら旧統一教会を擁護する発言等が散見される。このような有識者はごく一部に限られるが、このような論調は、日本社会が英語圏ではなく、日本の実情を対外的に発信することが難しいという現状を考慮しても、旧統一教会側の主張のみに依拠して、日本の実情を調査もしくは十分に理解せずになされたものであって、このような発言等は、学者としても、ジャーなリストとしても、弁護士としても、宗教家としても、あまりにも不公平かつ不公正であり、あまりにも軽率である。
このような有識者のごく一部に見られる言動は、被害者やその関係者等に対する誹謗中傷をさらに助長させている現状にあり、深刻な被害を被害者等に与えている。そして、このような言動は、被害者の泣き寝入りを助長しかねないものである。
当連絡会は、このような、日本の被害者の実情を理解せず、旧統一教会を無批判かつ軽率に擁護を行う有識者らに対し強く抗議するとともに、被害者の実情を調査せず、不公平かつ不公正、軽率な言動を行わないように強く求める |
| |
2 国等に対する声明の理由 |
| |
|
⑴ 不当寄附勧誘防止法の見直しについて |
| |
|
|
2022年12月10日成立の「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(以下「不当寄附勧誘防止法」という。)は、2023年6月1日までにすべての規定が施行され、今日で完全施行から約1年9カ月が経過したことになる。
不当寄附勧誘防止法は、成立までの審議期間が短く、十分な議論が尽くすことができないまま成立することとなってしまった。そのため、当時の消費者問題担当の内閣府特命担当大臣であった河野太郎大臣も、衆議院において、「法律が実際に施行され、運用される、その状況を見ながら今後のことをいろいろ考えていかなければならないんだろうと思っておりますし、この法案で100%全ていいとは思っておりません。」とした上で、見直しの議論のための「何らかの検討会、しっかりやってまいりたいと思います。」と答弁した。このような経緯により、不当寄附勧誘防止法には、附則5条で施行後2年を目途として法律の規定について検討し、必要な措置を講ずるものとされた。
また、参議院の付帯決議でも、附則5条の検討に当たっては、国会における審議において実効性に課題が示された点について検討し、必要な措置を講ずること、その際、不当な勧誘行為による被害者、被害対策に携わる弁護士等関係者を含む多様な者の意見を聴取しつつ、検討を進めることとされた。
同法施行後、正体を隠して勧誘する手法の問題点については、2023年12月14日に日本弁護士連合会から「霊感商法等の悪質商法により個人の意思決定の自由が阻害される被害に関する実効的な救済及び予防のための立法措置を求める意見書」が発出される等議論が進んでいる。また、2024年7月11日には、旧統一教会の献金勧誘行為について最高裁判所が初めて違法性の判断基準を示す判決を出し、かかる最高裁判決の基準に従った判断を示す裁判例も出されている。
そこで、当会は、不当寄附勧誘防止法の2年後見直しの時期を迎えるにあたって、この間の議論の進展を踏まえ、なお被害者救済及び被害抑止の実効性を確保するため、政府消費者庁及び国会において、見直しの議論を早急に開始するよう求める。
そして、法の見直しにあたって、①旧統一教会が行って来た違法不当な献金勧誘の手法に即した禁止行為を設定すること、②際限なく献金をさせられている信者と生活をともにする配偶者や子どもたち等の家族の被害を抜本的に救済できる制度を創設すること、③行政による迅速かつ実効的な被害救済、被害抑止ができるよう、行政措置の要件及び措置基準を見直すこと、④法の適用対象を個人や代表者等の定めがない宗教団体に拡大することを求める。
なお、不当寄附勧誘防止法の問題点については、当連絡会の令和6年9月21日付け声明を参照されたい。 |
| |
|
⑵ 解散命令及びその後の清算手続について |
| |
|
|
ア 声明の趣旨①について |
| |
|
|
最高裁判所は、令和7年3月3日、質問権行使に対する回答を拒んだとして、文部科学大臣が旧統一教会に過料を科すよう求めた手続において「法は、宗教団体が礼拝の施設その他の財産を所有してこれを維持運用するなどのために、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とし(法1条1項)宗教団体に法人格を付与し得ることとしているところ(法4条)、法81条1項1号が宗教法人の解散命令の事由として「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。」と規定している趣旨は、同号所定の事由がある場合には、宗教団体に法律上の能力を与えたままにしておくことが不適切となるところから、司法手続によって宗教法人を強制的に解散し、その法人格を失わしめることが可能となるようにすることにあると解される。」とした上で、「民法709条の不法行為を構成する行為は、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害するものであるから、当該行為が著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる事態を招来するものであってこれに関係した宗教団体に法律上の能力を与えたままにしておくことが不適切となることも、十分にあり得ることである。」として、民法の不法行為を構成する行為が法81条1項1号にいう「法令に違反」する行為に当たると適切な判断を示した。このような最高裁の判断は高く評価できるものである。
そして、旧統一教会が民法の不法行為を構成する行為を繰り返し行ってきたことはこれまでの多数の民事判決から明らかである。したがって、東京地方裁判所に対して、かかる最高裁決定の判断を踏まえ、速やかに解散命令を発令するよう求める。
|
| |
|
|
イ 声明の趣旨②について |
| |
|
|
宗教法人法は、清算人の職務を、①現務の結了、②債権の取立て及び債務の弁済、③残余財産の引渡しと規定したうえで(法49条の2第1項)、「清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。」(法49条の2第2項)とのみ定める。
しかし、前述のとおり、旧統一教会は、霊感商法や高額献金による被害は存在しない等として、自らが生み出した多数の甚大な被害に真摯に向き合っておらず、文部科学大臣による解散命令請求も信教の自由の侵害行為である等と非難し続けている。
このような旧統一教会の態度からすれば、清算手続における財産の隠匿、帳簿類の隠滅隠匿、手続への抵抗や不協力など様々な困難が伴うことが想定されるところである。
そのため宗教法人法81条1項又は2項前段で解散命令の決定を受けた宗教法人の場合の清算手続については、清算を迅速かつ円滑に進めるために、清算人の権限を明確化及び強化のための立法等の措置を講じることが必要である。
なお、清算人の権限強化の具体的内容については当連絡会の令和6年9月21日付け声明を参照されたい。 |
| |
|
|
ウ 声明の趣旨③について |
| |
|
|
宗教法人に清算手続の終了後もなお積極財産(残余財産)が残っている場合、宗教法人法50条1項では、その処分は、当該宗教法人の「規則で定めるところによる」こととされている。そのため残余財産は旧統一教会の指定する者に帰属する解釈になるとも考えられる。
この場合、清算手続が終了し残余財産が引き渡されてしまった後に脱会した信者は、旧統一教会にも残余財産を承継した者にも被害回復を求めることができなくなってしまうものと考えられる。
旧統一教会の被害については、少なくとも本人が脱会しないかぎり権利行使ができないという特殊性があり、先祖の因縁や地獄の恐怖で精神的に長く縛り付けられていることで、たとえ教団の教えがおかしいと思っても簡単に脱会に踏み切れない信者も多くいると考えられる。そうした信者が将来ようやく脱会に至った場合に、献金その他の被害を一切回復できないことになれば余りに酷である。
そこで、国に対し、宗教法人法81条1項又は2項前段で解散命令の決定を受けた宗教法人の場合の清算手続については、こうした清算後の脱会者の被害救済が図られるため立法等の措置を講ずるよう求める。 |
| |
|
⑶ 宗教等2世問題について |
| |
|
|
ア 声明の趣旨①について |
| |
|
|
「宗教等2世問題」について、現在発生している被害や今後発生するおそれのある被害については、行政による介入や福祉サービスによって解決する必要がある。この点については、当連絡会の2022年9月16日付け、2023年7月7日付け、2024年7月8日付けの各声明で述べたとおりである。
これに対し、既に発生した被害の回復を求める手段を司法手続によって実現する以外にない。このような既に発生した被害について、「宗教等2世」がその所属教団等に対して、自身の人生を奪われたことなどにつき慰謝料等の損害賠償請求を求める事例が存在する。このような損害賠償請求は、「宗教等2世」がこれまで被ってきた被害の回復のみならず、過去に区切りをつけ、これから将来に向かって幸せな生活を送るための重要な契機になるものである。そのため、「宗教等2世」が容易に法的救済への途にアクセスできるようにすることが必要である。 |
| |
|
|
イ 声明の趣旨②について |
| |
|
|
当連絡会の2024年9月21日付けの声明に記載したとおり、現在の裁判実務において、損害賠償の額の認定は低額に過ぎる。
「宗教上の信仰の選択は,単なる一時的単発的な商品の購入,サービスの享受とは異なり,その者の人生そのものに決定的かつ不可逆的な影響力を及ぼす可能性を秘めた誠に重大なもの」(青春を返せ訴訟一審判決、札幌地裁平成13年6月29日判決)であるところ、「宗教等2世」の多くは、生まれながらにしてその権利を真に自由な意思決定の下、行使する機会が与えられなかった。そして、信仰は、その者の全人格であり、あらゆる人生の分岐点における決断の指針となるものであるため、婚姻の自由、学問の自由、職業選択の自由に基づく各権利行使に決定的な影響を与えることとなり、「宗教等2世」は、宗教選択の自由を奪われ、恋愛、婚姻の自由を奪われ、進学、就職の自由を奪われ、その結果、成人後の人生を含む全人生において、全人格を奪われたと言える。
「宗教等2世」が被った人権侵害はこのように極めて重大なものであるから、相応の賠償がなされなければならない。
国には、慰謝料額算定の適正化に必要な立法措置等を講じることが求められている。 |
| |
|
|
ウ 声明の趣旨③について |
| |
|
|
声をあげた「宗教等2世」も含めた被害者ら、のみならずこうした旧統一教会の被害者らの救済に誠実に取り組んできた当連絡会所属の弁護士や牧師等の被害者関係者らに対して、この間、旧統一教会関係者らの誹謗中傷等が行われている。これに対しては、加害者側の旧統一教会は、その構成員である信者らに対し、被害者らへの誹謗中傷を控えるようにとの誠意ある行動もとっていないことから、むしろ誹謗中傷が助長されている状況にあり、誹謗中傷を恐れるあまり、旧統一教会の被害者の泣き寝入りを助長しかねない事態である。
今後、解散命令等が発出されると、さらに誹謗中傷がエスカレートするおそれがあることから、被害者からの相談を受けた行政、警察等の当局に対して、そのような行為が行われないよう、当該誹謗中傷に対し、刑事手続等を含む、速やかな厳正かつ適切な対処が求める。 |
| 第3 結語 |
| |
当連絡会は、旧統一教会に対する解散命令を目前に控え、本声明の実現に向けて、旧統一教会被害の救済及び防止という設立来の目的の下に、関係各所と積極的に協力・連携し、さらに考え方・意見・政党を問わず政治家の皆様とも協力・連携するなどして、引き続き努力していく決意である。 |
| 以上 |